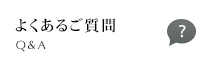論文・レポートを書くために
大学で論文・レポートを書く際には、いくつかのルールがあります。以下では、順に「剽窃」「レポート執筆の基本」「構成」「人名や資料の表記」「註と参考文献(書誌情報の書き方)」「著作権」について簡単に説明します。これらの作法と考え方をより深く学んでいただくため、入学後なるべく早い時期に総合教育科目「論述基礎」を受講することをお勧めします。また、文章を書くことじたいに慣れていないという方は、併せて同じく総合教育科目の「ことばと表現」にも取り組んでください。
(1)剽窃
まずレポート課題に取り組むに当たって、第一に意識していただきたい「剽窃」について説明します。一般の刊行物においては、文章を引用して出典を示さなかった場合、剽窃(他人の文章・語句・説などを盗んで使うこと、盗用)という不正行為にあたります。大学では、レポート課題の二次利用と剽窃に対しては単位不認定さらには退学処分も含め厳正に対応します。大学での学習の目的や意味を今一度考え、提出物の作成にあたってのルールを守り、自分自身で取り組んでください。引用する場合は、(5)註と参考文献(書誌情報の書き方)で示す註の書き方に則って、出典を正しく示してください。
インターネットやパソコンの普及に伴い、閲覧した他者のレポートや文章をそのまま自分の課題として提出するケースが発生しています。他人の著作を自分で書いた文章として二次利用すると、一切学習成果が上がらないばかりか、その著作者の権利を侵害することになってしまいます。
また自分自身が過去に書いた文章であっても、再利用に際しては出典の提示が必要です。自分自身の文章であっても盗用とみなされます。ブログやSNSで自分自身の意見を示している場合は、特に気をつけてください。
※科目で指定しているテキストについては参考文献としての明記は不要です。ただし、本文中で引用をした場合には出典元として記載が必要となります。
(2)レポート執筆の基本
大学で執筆するレポートは、中学校や高等学校で書く機会の多かった感想文とはまったく異なるものということを強く意識してください。同時に、ただ調べたことを書き連ねるだけの「調べ学習」とも違います。レポートとは「根拠」を示し、それに基づいて「考察」した報告書です。
レポートの基本の形は次のとおりです。
・段落をつける。
段落は、幾つかの文章をまとめたものです。論理的な文章を書くためには必須です。そして文章の冒頭は必ず1字あけます。行を改めた際の行頭も同様に1字あけてください。
・文末は「~である」とする。
日本語の文章では文末が「です・ます」か、「だ・である」に大きく分けられます。レポートでは後者の「だ・である」を基調として執筆してください。引用文を除き、「です・ます」と「だ・である」が混在しないように気をつけてください。
・タイトルをつける。
レポートの課題内容によっては、自分がどんなことを調査し考察したのかを、まず高らかに宣言する必要があります。それがタイトルです。レポートの内容を示す端的なタイトルを考えることも、レポート執筆の重要なポイントです。
・指定された字数を守る。
〇〇字程度と指示があった場合、その字数の±10パーセントを守ってください。指定字数より少なすぎるのはもちろん不十分ですが、超過するのも指定字数で適切にまとめきれていないことになります。
・問われたことのみを答える
テーマが設定されている課題では、そのテーマに焦点を絞って解答し、テーマから外れたことは書かないようにしましょう。
内容上最も重要なポイントは、「自身」と「他者」との意見を明確に区別することです。レポート執筆に際して読んだ文献を参考にする場合は、自他の意見を明確に書き分ける必要があります。無論、文献にあたらなければ、考察も出来ません。他者の意見をレポートで述べる場合は区別が付くように「註」を付けたり、「引用」するようにして下さい。註や引用の表記については4で示します。
(3)構成
レポート・論文は、「序論(はじめに)」「本論」「結論(おわりに)」の各部分で構成されますが、文字数の少ない課題では必ずしも「はじめに」「第1章」「第2章」「第3章」「おわりに」など目に見える形で章を立てる必要がない場合も多いです。ただし、章として明確に区分しない場合も、文章全体が序論、本論、結論の流れになるよう段落分けを工夫するなど、構成を意識して書きましょう。
以下は3,200字程度のレポートのひとつの構成例です(実際の各科目の課題にすべて適合するものではありません)。
【問題設定】(序論)
まず、レポートが解き明かそうとする課題は何かを記します。何をどう明らかにしようとして論文を書くのかを、基本的には疑問形で書きます。レポートでは、この課題があらかじめ指示されている場合がほとんどです。
【先行する言説や具体例の検証】(本論)
上の問題に対してテキストやこれまでの研究書などでどのようなことが言われてきたのかを紹介し、その議論の仕方やそれが扱っている事例の妥当性を検討します(言われてこなかったことがあればそれを指摘します)。
【自分の見解の提示】(結論)
レポートの結論を提示。必ず「課題」に答える形で。わかったこと、わからなかったことを記しても良いです。
(4)人名や資料の表記
■人名表記
・人名の後には生没年をつける。
例)歌川広重(1797~1858)
・漢字圏以外の人名には、初出時に原綴をつける。
例)フェリックス・ベアト(Felix Beato, 1834- c.1903)(「c.」は「頃」の意味で、年代が特定できない場合に用います。)
<日本人名の略称>
・近代以前は名前や号で略す。
例)(鈴木)春信、(狩野)探幽(最初に「鈴木春信」と書いたあと、次からは「春信」のみで「鈴木」を略せます。)
・近代以降は名字で呼ぶ。
例)萬(鐵五郎)、土門(拳)
・ただし日本画の場合は号で呼ぶことが多い。
例)(竹内)栖鳳、(橋本)関雪
<外国人名の略称>
・基本的には名字。
例)ピカソ、マネ
・二つ以上繋がった名字は、全部書く。
例)ファン・ゴッホ、トゥールーズ=ロートレック
・日本語に直すときのルール
①スペースはナカグロ。
例)Pablo Picasso パブロ・ピカソ
②ハイフンは等号。
例)Jean-Luc Godard ジャン=リュック・ゴダール
■標準的な数字・記号の使い方
・英数字は全角ではなく半角で書くのが一般的ですが、同じレポート内で統一されていればどちらでも構いません。
例)2023年度
・数字は縦書きは漢数字、横書きでは洋数字を使うことが一般的ですが、同じレポート内で統一されていればどちらでも構いません。
・「」カギカッコ引用文/論文・章の題名/シリーズ名/展覧会名などに用います。
例)論文:ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」
シリーズ:歌川広重の「東海道五十三次」
展覧会:「進化する映像」展
・『』二重カギカッコ書名/映画の題名などに用います。
例)書名:ミシェル・フーコー『言葉と物』、映画:『羅生門』
・《》二重ヤマガッコ主に造形芸術作品名(絵画、彫刻、インスタレーションなど)に使います。
例)ベラスケスの描いた《ラス・メニーナス》では…
・〈〉ヤマガッコ強調(カギカッコでも代用可)する場合です。ただしあまり使いません。
例)明治時代に、いわゆる〈美術史〉が創出され…
・〔〕キッコウ訳註や引用元にない補足説明に用います。
例)美術とはいわゆる国家のイデオロギー装置〔ルイ・アルチュセールによる概念〕でもあり…
なお、短いレポート(1,000字前後)では人名の原綴りや生没年などは必ずしも表記しなくて構いません。重要性に応じて付記するかどうかを判断してください。
(5)註と参考文献(書誌情報の書き方)
論文・レポート執筆にあたって文献・資料を本文中に引用する、もしくは参照させる場合は、その典拠として用いた文献・資料の書誌情報・資料情報を明示する必要があります。以下に、註と参考文献に関する、本学で用いている論文執筆ルールを記します。なお、実際には学校、学問領域、学術誌によってそれぞれの書式が採用されており(本文中に著者名と文献発行年を括弧書きで示し、本文末尾に引用文献リストを列挙する方法など)、また本学でも科目や課題の性格によって特別な書き方が指定される場合もありますので、疑問があればコンシェルジュを通じて担当教員 に相談してください。
①註
註には、レポート本文で考察の論拠として参考文献の内容を示す際に用いる【A文献註】と本文では書きにくい補足的な説明を記す【B補足註・意味註】の主に2通りの用途があります。
※原則、註に書誌情報を示す場合には、参照箇所のページ番号を記載します。
【A文献註】
文献註は、レポート本文で考察の論拠として参考文献の内容を示す際に用いるものです。
レポート本文で参考文献の内容を記載することを「引用」といいます。引用には、さらに直接引用と間接引用があります。
■直接引用
直接引用とは、参考文献にある文言を「 」などでくくり、論拠として提示するものです。その際にレポート本文で「 」の後に(1)(2)…などを表記し、レポート本文の末尾で出典を明記します。
例)
・レポート本文:
伝統とは何か。本科目のテキストで野村朋弘は「伝統とは新たに創出されたものが、普遍的な価値を持ち、永く後世に伝わること」(1)と述べている。
・註の書式:
註(1)野村朋弘「第 5章今日の日本における「伝統」の成立」野村朋弘編『日本文化の源流を探る』京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎、2014年、51頁。
■間接引用
間接引用とは、参考文献にある文章をまとめなおし、要約して提示するものです。
例)
・レポート本文:
伝統という価値観は時代によって変容する。野村朋弘が指摘するように、伝統を理解するにはその歴史性を把握することが必要である (1)。
・註の書式:
註(1)野村朋弘「第 5章今日の日本における「伝統」の成立」野村朋弘編『日本文化の源流を探る』京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎、2014年、51頁。
直接引用をする場合は「 」に入れて出典を明記すること、また間接引用であっても、出典を明記することが必要です。出典を明記せずに引用をした場合は、剽窃とみなされます。ただし引用が多くなりすぎると、レポートの指定字数内で自分の意見を十分に示すことができなくなります。適切にまとめて引用し出典を明記することが、書き方として効果的です。
【B補足註・意味註】
補足註は本文の内容の補足的な説明をし、意味註は一般的ではない用語の意味を説明します。
例)補足註
・レポート本文:
各地の遺跡や史跡においては、その整備に関して、しばしば復元建物が建てられる(1)。
・註の書式:
註(1)復元建物の嚆矢は登呂遺跡とされている(青柳憲昌「関野克の登呂遺跡住居復原案の形成過程と「復元」の基本方針」『日本建築学会計画系論文集』654、日本建築学会、2010年、2073-2080頁)。
例)意味註
・レポート本文:
「花鳥文刺繍幡残片(南倉47)」では芥子縫い(1)という刺繍技法で花や蕾が表されている。
・註の書式:
註(1)「芥子粒のような小さな点を表す刺繍技法。点を連ねることで輪郭線や、霞のような暈しを表したりする」(奈良国立博物館編『第五十八回「正倉院展」目録』奈良国立博物館、145頁)。
②参考文献
上記の註で示す他、レポート作成過程に関わって、参照した文献を提示するのが参考文献です。レポートの考察で直接的に参照する場合は、①註 の方法で示してください。ただし、レポート作成に関して参照した参考文献すべてを提示する必要はありません。課題の趣旨に応じて「参考とすべき文献」を提示するということに注意してください。
■書誌情報の書き方
ここに記載例がないものについては、以下の点を参考にして書き方を考えましょう。
①第三者(レポートの読み手)が実際にその文献を閲覧しようとしたときに必要な情報(タイトル、発行年、出版社、著者など)は何かを考えて記載する。
②タイトル、発行年、著者等を記載する順序や、細かい表記の仕方(体裁)は1つのレポート内で統一する。
③他の論文や書籍等の書誌情報がどのように記載されているか、類似例を探してみる。
④論文・レポートでの書誌情報の書き方が解説されている本やサイトを調べてみる。
<和書の場合>
(1)著者名「(2)論文名」(3)編者名『(4)本・雑誌の題名』(5)翻訳者名、(6)出版社名、(7)出版年、(8)ページ番号(1ページの場合:〇頁、複数ページの場合:〇-〇頁)。
・単著
例)木下直之『写真画論』岩波書店、1996年。
・共著(著者、編者が2名の場合)
例)井上治・森田都紀編『伝統文化 研究編』京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局 藝術学舎、2022年。
・共著(著者、編者が3名以上の場合)
例)小川直之 他編『暮らしに息づく伝承文化』京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局 藝術学舎、2014年。
*1番目に記載されている著者(または編者)名を記載し、2人目以降は省略可
・本の中の論文
例)北澤憲昭「文展の創設」、『境界の美術史 ~「美術」形成史ノート』ブリュッケ、2000年。
・図書に収録される特定の章や論文
例)港千尋「伝神絵」、小林康夫・松浦寿輝編『イメージ ~不可視なるものの強度』東京大学出版会、2000年、35-60頁。
・雑誌論文
例)上村博「ユートピアへのノスタルジー」、『京都造形芸術大学GENESIS』第20号、2015年、47-58頁。
・単著(翻訳)
例)スーザン・ソンタグ『写真論』近藤耕人訳、晶文社、1979年。
・図書に収録される特定の章や論文(翻訳)
例)カルロ・ギンズブルグ「徴候 ~推論的範例の根元」、『神話・寓意・徴候』竹山博英訳、せりか書房、1988年、177-226頁。
* ただし、註の文章の中に書誌情報を埋め込む場合、題名以後はカッコで括ること。
例)J・クレーリーの「近代化する視覚」(ハル・フォスター編『視覚論』榑沼範久訳、平凡社、2000年)によれば…
・「改訂版」「第〇版」等の場合
例)村井康彦監修『京都学史料』京都造形芸術大学、2009年(初版 2003年)
*実際に参照した版の出版年に加え、初版の出版年も併記する
<洋書の場合>
(1)著者名, “(2)論文名”,(3)編者名,ed.(編者が複数名の場合には”eds.”),(4)本・雑誌の題名(イタリック), (5)出版社のある都市名: (6)出版社名, (7)出版年, (8)ページ番号(1ページの場合:p.〇、複数ページの場合:pp.〇-〇).
・単著
例)James R. Ryan, Picturing Empire: Photography and the Visualization of the British Empire, Chicago: University of Chicago Press, 1997.
・図書に収録される特定の章や論文
例)Daniel J. Boorstin, “From Traveler to Tourist: The Lost Art of Travel”, The Image: or, What Happened to the American Dream, New York: Atheneum, 1962, pp.77-117.
<ウェブサイトの場合>
例) 正倉院宝物検索「御袈裟箱 第1号」解説文、宮内庁ホームページhttps://shosoin.kunaicho.go.jp/treasures?id=0000010014(2024年9月20日閲覧)
<電子書籍の場合>
書誌情報の記し方については印刷された文献と同じです。ただしページ数は閲覧環境によって変わるため、章、節、段落によって引用箇所を示してください。
例) 鷲田清一『素手のふるまいアートがさぐる〈未知の社会性〉』朝日新聞社出版、2016年、第6章「〈社会的なもの〉」、第2節「徴候として現れる社会」、第2段落。
<ジャパンナレッジの場合>
(1)項目の著者名「(2)調べた項目」(3)編者『(4)辞典名』(5)出版社、ジャパンナレッジ、(6) URL((7)閲覧日)
※(1)項目の著者名は不明であれば不要です。
※PDF viewerで参照するものは、<電子書籍の場合>を参考にしてください。
例)五味文彦「保元の乱」国史大辞典編集委員会編『国史大辞典』吉川弘文館、ジャパンナレッジ、https://na07vpn.kyoto-art.ac.jp(2024年12月19日閲覧)
■図版の引用について
図版を複写して論文・レポートに利用する際のルールは世間では一定ではありません。市販本や雑誌論文でも図版出典が明記されていない場合があります。ただし、著作物の引用にかかわりますので、何らかの出版物から複写して図版を用いる場合は、出典を明記するように心がけてください。
図版のキャプションとして記すか、あるいは、論文・レポート末尾の図版リストに引用元や、また図版の用途によっては作例の大きさや年代、所有者などの関連情報も記してください。
(6)著作権
・著作権Q&Aも参考に。
芸術大学に集う私たちにとって、自身の想いを自由に表現しようとすることと、他者の表現を尊重することとは等しく大切なことです。知らず知らずのことであっても自分の表現が他者の表現を侵害することに繋がれば大変悲しいことです。ひとりひとりがお互いの制作創作活動を尊重するために必要な最低限度の知識を共有できるようairU学習ガイド > 5.学習のアドバイス > レポート作成にあたって > 著作権についてにQ&Aがまとめてあります。身近で具体的な事柄が中心ですので、よく読んで役立ててください。
(7)表現の自由
表現の自由は日本国憲法第21条で認められている国民の権利であり、本学でも尊重しています。レポートや作品制作において大学教育の一環として講評し成績評価を行いますが、レポートや作品そのものを否定することはありません。ただし、表現の自由は絶対的に、かつ無制限に保証されるものではなく、公共の福祉など社会的配慮をもって合理的に制限を受けることがあります。
詳しく示すと他者の個性や出自、また民族、地域、国、宗教、思想などを侮辱する表現、差別やヘイトスピーチ等の表現、歴史を改ざんし歪曲する表現は避けるべきと考えます。自他の表現の自由を尊重しつつ、学業を追究することにつとめてください。